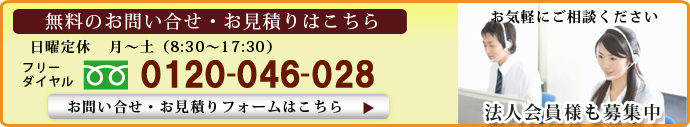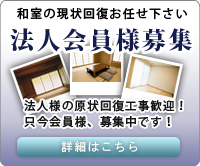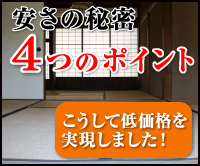畳の機能
夏はべたつかずサラっとしていて涼しく、冬はひやっとせず暖かい畳。
普段生活の一部に溶け込んでいる畳の良さについて、私達はなかなか意識はしないものです。畳に使われるい草には湿度の高い日本の環境でも快適に暮らす為の先人の知恵が使われているのです。
畳の調湿機能
まず畳の機能としてあげるのは、優れた調湿効果。和室の空気がジメジメと重く感じられることは少ないと思います。
それはい草が空気中の水分を吸収し、湿度を下げコントロールしているからです。
湿度の高い日は水分を吸収し、湿度の低い日は放出とい草が呼吸しているから私達は快適に過ごせるのです。
表替えをしたばかりの畳や長期の締め切りや機密性の高いマンションでは、カビに注意する必要があります。
畳の上にじゅうたんなど敷物をすると、いぐさの呼吸を妨げてしまい、ダニカビの棲家になりますので避けましょう。
<窓を空けた状態>

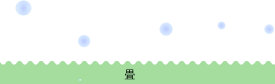
畳が吸った水分を放出
湿度の高い日に吸った水分を晴れた日や換気したに放出します。お部屋の湿度を上げますから、お部屋の乾燥を防いで快適な湿度に調整します。
<窓を閉め切った状態>

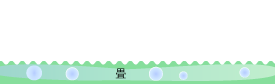
畳が空気中の水分を吸収
い草が空気中の湿気(水分)を吸い込みますから、ジメジメと重い空気になるのを防ぎます。お部屋の湿度を下げて快適な湿度に調整します。
表替えをした直後は、1日に1回最低1週間できる限りたくさん換気をしてください。
畳の防音機能

畳には防音効果も発揮します。
い草や床がクッション代わりとなり衝撃を和らげたり、音を吸収してくれます。
実は小型犬など室内ペットにも足腰への負担の少ない畳が適しています。ペットと暮らす和室には、足爪が擦れても毛羽立ちにくい、汚れにくいといった丈夫な健康畳がおすすめです。
ただし、優れた防音効果を発揮するのはワラを使った昔ながらの重厚な畳床で、現代によくある軽量で簡易的な畳材(ウレタンフォーム、スタイロ、発泡スチロール)などは残念ながら、効果はほとんど期待できません。
畳の豆知識
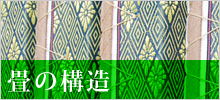
畳は床と畳表(ござ)の二層からなります。それを縁であわせたものが畳となるわけです。畳の構造について
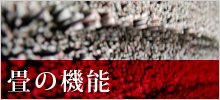
畳には調湿効果機能があり、私達の暮らしに様々なプラスをもたらしてくれています。 畳の機能について
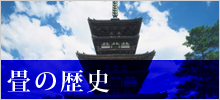
畳はいつどのようにして始まったのでしょう?
畳の歴史を紐解きます。
畳の歴史について

畳を長くお使いいただくために、日頃から出来るお手入れ方法をご紹介します。畳のお手入れ方法について

耳慣れない畳の専門用語。解説つきでまとめました。畳の用語集を見る

お客様からよくいただく畳のご質問をまとめました。お問い合せ前にご覧ください。畳のQ&Aを見る